41プレゼント

西尾市岩瀬文庫
蔦重や北斎 時超える本の面白さ

西尾市岩瀬文庫では、江戸時代までの「古典籍」と呼ばれる書物を中心に8万冊余りを所蔵します。その中には、放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で話題の蔦屋重三郎(蔦重)を版元とした本もあります。
「箱入娘面屋人魚(はこいりむすめめんやにんぎょう)」は浦島太郎の後日談を描くパロディーです。洒落(しゃれ)や風刺をきかせた大人向け絵入り小説「黄表紙」の一冊で、山東京伝が手がけた作品です。
主人公の漁師は、船に飛び込んできた人魚を妻にしますが、実は浦島太郎が竜宮城で浮気したコイとの間の子でした。貧しさから人魚は尾ひれを隠して吉原で働きますが、体が生臭くて失敗。次に「人魚嘗所」を始めると人魚をなめた人は少し若返ると大評判。なめ過ぎて子どもになってしまった漁師は玉手箱を開くと程よい青年の姿に。人魚も人間になり幸せに暮らしましたとさ、という物語です。
序文には、本人像として現在よく使われる蔦重の姿が。ページ上と着物の袖にある山にツタの葉のマークは、版元印です。筆を断つと言う京伝に、長い付き合いに免じて頼み込んで書いてもらった一冊なので、ぜひご覧くださいと口上を述べています。
江戸の本屋は蔦重だけではありません。山口屋忠右衛門が出した「化物和本草(ばけものやまとほんぞう)」の挿絵を描いたのは、かの葛飾北斎です。当時の博物誌「大和本草」風に、架空の化け物たちの生態をもっともらしく解説しています。「四四真鍮の鼡(しししんちゅうのねずみ)」は仏教由来の「獅子身中の虫」をもじった真鍮の化け物で、「しんチュウ」と鳴くのだとか。この姿がまたかわいらしいのです。
これらの本は、古典や世相を知らないと分からない内容が多く、庶民の教養の高さに驚かされます。一方で今の漫画に通じるキャラクターも登場し、時代を超えて楽しめます。当時の人々と面白さを共有できるのも実物が残っていてこそ。18歳以上の来館者は閲覧室でほぼ全ての古典籍を読むことができます。その本はもしかしたら蔦重も手に取っていたかもしれませんよ。
(聞き手・中村さやか)
《西尾市岩瀬文庫》 愛知県西尾市亀沢町480(☎0563・56・2459)。午前9時~午後5時。祝休を除く月、原則第3木、12月1日~9日、年末年始休み。2点は「江戸の出版文化と蔦屋重三郎 楽しすぎるよ!江戸の本」(11月30日まで)で展示中。
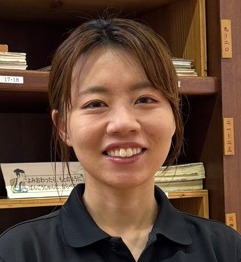
学芸員・青木眞美さん あおき・まみ 西尾市出身。愛知県立大学で文献史学を学び、江戸時代の古文書などを研究。専門は日本近世史。西尾市岩瀬文庫で企画展や調査を担当。 |




